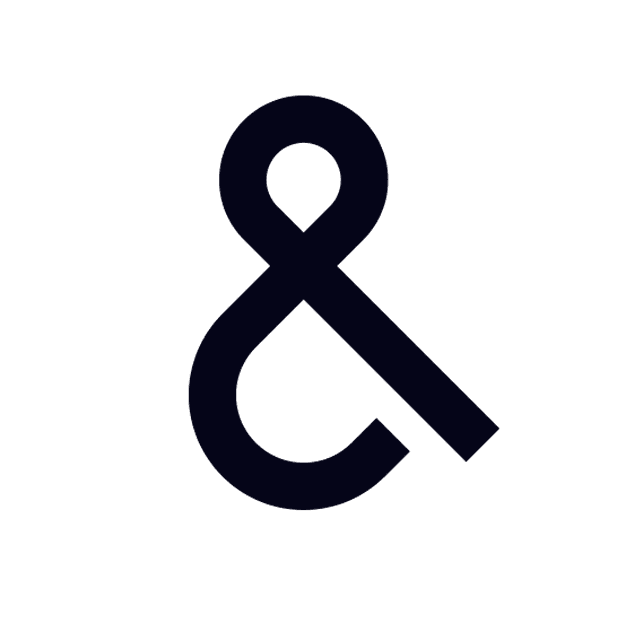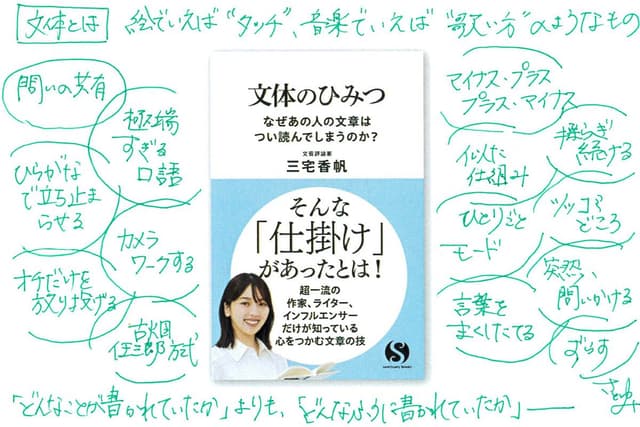〈住人プロフィール〉
52歳(会社員・男性)
賃貸戸建て・2LDK・JR横須賀線 逗子駅・神奈川県三浦郡葉山町
入居8年・築年数60年・ひとり暮らし
一通の応募メールから
昨年、番外編『神奈川の台所』掲載のため、取材者を募集した。応募メールのひとつに、これはあの話に出てきたお連れ合いではないかと思うものがあった。
318回『「好き」だけでは頑張り切れない食の世界で、彼女が見つけたもの』である。
住人の女性、Mさん(48歳)は、働き方改革という言葉がない時代に、ブラックな現場で製菓の商品開発に従事。体を壊し、大好きな食の世界から足を洗おうと決意した先で、たまたま葉山在住の料理家に出会った。その料理家によって、人生観が一変したという話だった。該当回の一節を引用する。
メディアでも引っ張りだこのその料理家は、どんなに体に良いものでも、「おいしくないと続かない」が持論だ。
おいしければ笑顔になる。なにを使うか以上に、みなで笑いながら食卓を囲む喜びを尊び、それこそが心の栄養、支えになると、一貫して伝えた。
「葉山に引っ越しておいでよ」と、よく言われた。仕事を通り越して「家族のような人だった」と彼女は述懐する。
過去形なのは、3年前に料理家は逝去したからである。
Mさんは導かれるようにして、その後、逗子葉山に越した。
前述の、神奈川からの応募は、癌(がん)で亡くなった料理家の夫のようだ。
早速連絡を取ると、「318回を読んで応募しました」とのことだった。
本連載は、今月で14年目に入る。
ときおり、「結婚した」「子どもが生まれた」「人生の再出発をした」というメールや、「大切な人を見送りました」というお知らせをいただくようになった。
いうまでもなく、取材した日がゴールではない。人生も、台所を巡る物語もその先も続く。
私はMさんの台所の執筆時、その料理家のレシピや生前のインタビュー記事をいくつか読んだ。知れば知るほど人間味あふれる人物で、ああご存命のうちにひとめ会いたかったと率直に思った。Mさんにもそう漏らしたと思う。
今回の台所の主は、妻の闘病を機に葉山に転居。その暮らしのなかで野菜作りや発酵料理、保存食作りの楽しさに目ざめ、彼もまた、Mさんのように価値観が大きく変わったという。
みぢかな人たちにたくさんの影響を与えた女性が遺(のこ)した台所は、いったいどんな空間だろう。彼にはどんな変化があり、今どんなふうに暮らしを紡いでいるのか。
新春特別回として、「東京の台所」その後の物語をお送りする。
忘れられないお弁当
学生時代はひとり暮らしだったが、自炊はカレーか鍋くらい。27歳で最初の結婚をするまで、彼はほぼ外食という毎日だった。
「めちゃくちゃ忙しい広告業界に就職したので、新婚感もあまりなかったですね。僕は家でほとんど食事できなかった。それだけが理由ではありませんが、結婚生活は11カ月で終わりました」
CMプロデューサーで、会食も多い。元々料理は得意でもなく、台所に立つことがないまま31歳に。
たまたま合コンで、目の前に座った女性が同い年だった。
話が合い、その後やりとりを経て、初めてふたりだけで会うことになった。
「そのときお弁当を作ってきたんです。おにぎりと卵焼きと浅漬けと唐揚げが入っていた。あとから聞いたら、彼女は当時、料理学校の留学から帰ったばかりで、バイトをしていてお金がなかったらしい。僕は、ドライブデートにお弁当を持参する人は初めてで驚いたし、素朴ですごくおいしくて感動しました。この人の料理を食べる人は幸せだろうなあと、ぼんやり思いました」
初めて家に来たときは、親子丼を作ってくれた。これもまたふわふわトロリとした食感で何杯でもいけそうだ。好みの味に、彼は思わず声が漏れた。
「めちゃくちゃうまいじゃん!」
誕生日プレゼントは、手作りのパンとイチゴジャムだった。
「あ、こういう感覚っていいなと。ふつう誕生日っていうと、ついブランドものとかになりがちじゃないですか。彼女は実家が専業農家で、僕の母の実家もそう。母も、たまに焼きリンゴやドーナツを作ってくれていたので、こういう手作りのおやつって、好きだったよなと思い出しました。わりと金銭感覚も似ていましたね」
一緒に暮らし始めると、さらに実感した。──この人の作る料理、全部うまいかも。
川崎市のタワマンの30階に1年同棲(どうせい)した後、34歳で結婚。彼は前の経験も踏まえ、「平日は忙しいので100パーセント外食になる。食事は作らなくていいよ」と伝えた。
いっぽう彼女も徐々に、フードコーディネーターや管理栄養士としてレシピ監修など食の仕事が増えていった。
そしてあるとき、開店予定の飲食店のグランシェフ(総料理長)に、と声がかかる。
「やりたいことがある人との結婚を望んでいたので、尊重したかったのですが、飲食店だけは反対しました。子どもが欲しかったので……」
彼女は、両方あきらめたくないと主張。
しかし、いざ始めると、何事にも真剣で責任感の強い彼女は、寝袋を持ち込んで働く日々に。休日も食材の生産者を訪ねて地方に出向き、試作まである。
3カ月後には「ごめん両方は無理だわ」と謝られた。仕事を選んだのだ。
彼はもやもやしつつも、それ以降子どものことをじっくり話すことはなかった。なぜなら、ほどなくして、彼女に初期の癌が見つかったからだ。
タワマン30階から葉山の平屋へ
病気を機にシェフを降りたが、そこから彼女は、料理家として想定以上にどんどん忙しくなっていった。
勤務時代、地方の農家や漁師、昔ながらの製法で醬油(しょうゆ)や甘酒を作る生産者たちに出会った。そこで大きな刺激を受け、発酵文化と家庭料理を追究するようになったためだ。
折しも塩こうじブームが到来していた。
季節感と素材の持ち味を大切にした、日常にすっとなじむ彼女の気負わぬレシピはさまざまなメディアで注目され、テレビ、雑誌、レシピ本、病院食、ときに海外の料理学校から招かれるなどが、ひきもきらない。
タワマンで暮らした12年のうち後半は、「互いに今日どこにいるのかわからず、“今どこ?”“海外だよ”という日もあるくらい」忙しかった。
ところがやがて、病気が再発した。
彼女はこれからどんな料理を作っていきたいか。彼は徹夜もざらで、つねに売り上げを追いかけ、自分の時間は一切ないという働き方を変えたい。ふたりの思考のベクトルが、一致した。
「土に近いところで暮らそう」
こうして葉山で、築50年余の平屋に出会った。
「彼女の料理は土に近いところが似合うと思ったし、迷いはありませんでした。それまで並走してこなかった我々が、人生のカウントダウンを意識することで初めて、突然同じ方向を見るようになった。そんな不思議なタイミングでしたね」
2018年8月。2LDKの元米軍ハウス。裏には小さな畑があり、台所は二口コンロで傍らに勝手口と土間があり、どこもかしこも隙間風だらけの貸家に越してきた。